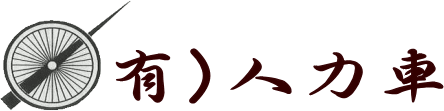LEVEL-05 文法 形(活用形)
| 形(活用形) | |||
| て形 | ない形 | 辞書形 | た形 |
| 「て形」とは、動詞の活用の一種で、「~て/で」で終わるものです。たとえば、「話して」、「見て」、「来て」のように表現されます。 「て形」は、二つの文をつなげ、一つの文にまとめるときに使われます。動詞、イ形容詞、ナ形容詞、名詞は「て形」を使って、前文と後文をつなげることができます。たとえば、「傘を持って、出かけます」のように表現されます。 「て形」は、日本語文法における重要な活用です。さまざまな文法形式を作るときに使われるため、特に学習が必要です。 「て形」は、辞書形の一番最後の一字に「て」をつけることで作ります。「マス形」から覚える時は「マス形」の「ます」をとって、「て」をつけます。 | 「~ない」の形を「ない形」といいます。たとえば、「食べない」のように「ます」が「ない」になる形です 「ます形」から「ない形」を作るには、2グループの動詞は「ます」が「ない」になるだけです。1グループは「ます」の前の母音が「あ」になって「ない」が付きます。ただし「い」は「わ」になります。 たとえば、「食べます」は「食べ(ない)」となります。「寝ます」→「寝(ない)」「出ます」→「出(ない)」となります 「ない形」は、動詞の活用形の一つです。次のように使われます。 辛い食べ物を食べないでください 「ない形」の過去形は「なかった形」です。「-ない」を「-なかった」にかえることで作れます | 辞書形とは、動詞の最も基本的な形で、「話す」「食べる」「する」のように、まさに“辞書に載っている形”です。 辞書形は、辞書の見出しに使われる形であり、またさまざまな活用形を作るときの基本になるので覚えてください。動詞の場合は、「普通形非過去肯定」の形と同じです。 動詞の辞書形は、不特定活用・現在・3人称単数形である。語尾は、以下の-ik動詞を除き、通常はゼロ(∅)です。 日本語教育では、そのような形の変化を「辞書形」(辞書に出てくる形、たとえば「食べる」)を中心にして記述するのが常です | 「た形」とは、日本語の動詞の活用形の一種で、「~た(だ)」になる形を指します。たとえば、「食べた」「書いた」「起きた」などが「た形」です 「た形」は、助動詞「タ」がついた形で、「過去」を表します。また、「完了・未完了」的な側面も表すことができます。 「た形」は、「て形」の「て」を「た」にすることで作ることができます。たとえば、「のんだ」のように「で」は「だ」に、「いって」のような特別な活用も「いった」になります。 「た形」の基本的な用法は、過去の出来事や性質、現在につながる過去の出来事やその結果などです。たとえば、「先週の日曜日、家族で旅行に行った」「昨日の夜、急に頭が痛くなった」などです |
| 普通形 | 可能動詞 | 意向形 | 命令形 |
| 普通形(Plain form)とは、日本語動詞の活用形の1つで、最も基本的な形である「辞書形」「ない形」「た形」「なかった形」の4つを指します。 普通形は、カジュアルな場面では「ます形」の代わりに使われます。親しい友人間の会話や、小説や日記、論文、レポートなどで使われます。 普通形は、文中で「連体・引用」という機能を果たす形で、「丁寧かどうか」とは関係ありません 普通形と普通体は異なる概念です。普通体は「丁寧かどうか」という話し方のことで、主に文末で用いられます。普通形は、主に文中で「連体・引用」という機能を果たす形です。 | 可能動詞とは、五段活用の動詞を下一段活用の動詞に変えて、可能(行為をすることができること)の意味を表す動詞です 「書く」に対する「書ける」、「打つ」に対する「打てる」の類を可能動詞といいます。 可能動詞の特徴は次のとおりです。 一語で「~できる」という意味を表す。 必ず下一段活用(「ない」を付けたときの直前の音がエ段の音)になる。 五段活用の動詞がもとになっている。 命令形はない。 可能動詞は室町時代に発生し、次第に元来の可能の助動詞「〜れる」を用いる語法に取って代わりました。 現在では、五段活用以外の動詞からできた「見れる」「来れる」などをも、可能動詞と認める場合があります。 | 意向形とは、動詞の活用形のひとつで、意向や勧誘を表す形です。共通語では「書こう」「見よう」のように使われます たとえば、「一生懸命がんばりましょう」は「一生懸命がんばろう」のように使えます。「勉強しましょう」の普通形は「勉強しよう」で、「しよう」は「します」の意向形です。 意向形は、仙北地方、平鹿地方、雄勝地方、由利地方など県南部方言では比較的多く用いられますが、それ以外では意思を基本形で表すことが多いです。 意向形は単独で使うとひとりごとや勧誘の意味を表します。話し手がある行為をする意志があることを聞き手に伝える場合には、意向形に「と思います」(普通形「と思う」)をつけて使うのがふつうです。 | 命令形とは、国文法で活用形の1つで、命令の意を表して言い切る形です。六活用形の第6番目に置かれます 命令形は、動詞や助動詞の活用形の1つで、その動作の実行や状態の実現を相手に求めるときの語形です。たとえば、「書け」「見ろ」「起きよ」「来い」などの類が命令形です。 英語の命令形は、動詞の原形で始まり、相手に命令、依頼、助言などをする際に用いる文です。主語を省略し、文を動詞の原形で始めるのが「命令形」です |
| 禁止形 | 条件形 | 受身動詞 | 使役動詞 |
| 禁止形とは、禁止を表す否定命令文の形式で、動詞の終止形に終助詞「な」を付けた「動詞+な」です。 禁止形は、命令形と同じで、とても強い言い方です。自分より下の人にしか使えません。 男性同士の会話の場合は、「禁止形」+「よ」を使う場合が多いです。 禁止表現の例文は次のとおりです。 法律、規則に違反することを禁止しています。 今は、大きな声で話してはいけません。 「~てはいけません」は、法律、規則に違反することを禁止しています。 | 条件形とは、仮定条件を表す動詞の形で、「ば」で終わるためこの名前がついています 「行けば」「書けば」のように「行け」「書け」の類が条件形です。 条件形は「-たら」や「-と」などで表現することもできます。 また、形式的に否定「ない」と条件を表す形態素を含む動詞形を否定条件形と呼びます | 受身動詞とは、主語が動作や作用を「する」のではなく「される」という表現形式(=態)を指します 日本語では「れる」「られる」などの助動詞によって表現されます。英語では「be動詞+過去分詞」という叙述形式で表現されます。 受身動詞の例としては、「捕まえられる」「見つけられる」「負かされる」「やぶられる」「知られる」「授けられる」「教えられる」「言いづけられる」「言付けられる」「貸される」「預けられる」などがあります。 受身動詞の例文としては、「田中さんが私を褒める」に対して「私が田中さんに褒められる」といった状態が受身です。 | 使役動詞とは、「(〜に)…させる」という意味を持つ動詞です。たとえば、「先生が陳さんにテキストを読ませる」などです。 使役とは、「使(=させる)、役(=仕事、行動)」のことです。つまり、使役とは、誰かに仕事をさせることです。 使役は、上下関係のある場面で、立場が上の人(先生、上司、親など)が、立場が下の人に「〇〇をしなさい!」と無理矢理何かをさせるときに使われます。 使役は、動詞や助動詞、動詞の接尾辞によって構文が導かれます。 |
| 尊敬語 | 謙譲語 | ||
| 尊敬語とは、話し手が聞き手や話題の主、またはその動作・状態などを高めて待遇することを言い表す敬語です 尊敬語には、次のようなものがあります。 「いらっしゃる」「めしあがる」などの敬語動詞 接辞「お」「ご」(「お荷物」「御主人」) 助動詞「れる」「られる」 補助動詞「お…になる」(「書かれる」「お読みになる」) 尊敬語は、目上の人や自分より立場が上の人をうやまい、相手を立てる気持ちを表す敬語です。たとえば、「先生がおっしゃったとおり~」など、先生や社長、上司などの自分より目上の他人(家族、親戚ではない)が主語になります。 尊敬語と謙譲語を正しく使い分けるには、その動作が、だれの動作かを考えます。相手や話題になる人の動作の場合は尊敬語、自分や身内の動作の場合はけんじょう語を使いましょう | 謙譲語とは、敬語の一種で、話し手が自分や自分の側にあると判断されるものに対して、へりくだった表現をすることで、相対的に相手や話中の人に対して敬意を表す言葉です 謙譲語の例としては、「わたくし」「うかがう」「いただく」「伺う」「参る」「申す」などがあります。 謙譲語は、尊敬語のように相手を高めるのではなく、自分がへりくだることで相手を立て、敬意を表す敬語です。謙譲語における動作主は自分か身内です。目上の人間が動作主のときに謙譲語を使うのは不適切なので要注意です。 謙譲語には小分類があり、「謙譲語Ⅰ」と「謙譲語Ⅱ(丁重語)」の2つに分けられます。 | ||